スウィート・カントリー・スウィート
WC027★★★SWEET COUNTRY SUITEーLarry Murray ('71)

- アーティスト: Larry Murray
- 出版社/メーカー: Fallout
- 発売日: 2006/08/22
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
こういうのを聞いてるとナッシュヴィル産のカントリーロックと、カリフォルニア産のものは全然違うなあと感じます。メロディアスでフォーキーな1枚。後期バーズがとりあげた”Bugler”の作者ヴァージョンが聴けます。若きJ・D・サウザーがdsとして参加しています。
原盤 Verve Forecast:FTS-3090 71年リリース
★★AMERICAN BEAUTYーGrateful Dead ('70)

- アーティスト: Grateful Dead
- 出版社/メーカー: Rhino
- 発売日: 2004/04/02
- メディア: CD
- この商品を含むブログ (3件) を見る
サン・フランシスコが、フラワー・ムーヴメントと共に大いに脚光を浴びたのは67~68年頃です。サマー・オブ・ラヴといわれた67年夏のヒッピー達を中心とした連帯的な盛り上がりは、69年12月のシスコ郊外のオルタモントの悲劇といわれたストーンズのフリー・コンサート(黒人観客が会場警備のヘルズ・エンジェルズに殺害されたという事件)をきっかけに、急速にしぼみ、すべては幻想だったと自覚してゆくのです。
69年に「Volunteers」という大傑作を出したジェファーソン・エアプレインはこの年(70年)には、アルバムを出していません。一方シスコロックのもう一つの雄、グレイトフル・デッドは「Workingman's Dead」、「American Beauty」という2枚を短期間のうちにリリースしています。
69年の2枚組の「Live/Dead」でサイケデリックなステージをドキュメント化したデッドは、交流のあったCS&Nに影響されたハーモニーを生かした”Uncle John's Band”を録音。これを含む「Workingman」は、それまでのデッドよりも聞きやすいと評判でした。デッド流カントリー・ロックへのチャレンジはさらに続き「American」では、かなりユルサを感じさせる1枚で、昔は通して聞いてられなかったのですが、久々に聞くと結構ハマります。ジェリー・ガルシアが当時ニュー・ライダーズ・オブ・パープル・セージという趣味バンドを始めていたこともあって、カントリー・ロックの要素が前作よりも色濃いです。もちろんここでの音は学究的なカントリー・ロックではなく、仲間でわいわい的なものです。デッドの中ではロックンロール的な曲を書くことが多いボブ・ウィアが”Sugar Magnolia”、”Truckin'”という2大名曲をものにしているのはすごい。
原盤 Warner Brothers:WS1893 70年11月リリース。
テレンス・ボイラン(Terence Boylan)

- アーティスト: Terence Boylan
- 出版社/メーカー: Wounded Bird Records
- 発売日: 2007/07/17
- メディア: CD
- 購入: 1人 クリック: 7回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
ゲイリー・ボイル(Gary Boyle)

- アーティスト: GARY BOYLE
- 出版社/メーカー: ESOTERIC
- 発売日: 2012/01/30
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
ビリー・ブラッグ(Billy Bragg)
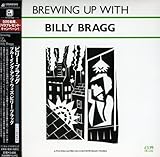
BREWING UP WITH BILLY BRAGG(紙ジャケット仕様)
- アーティスト: ビリー・ブラッグ,モリッシー,マー
- 出版社/メーカー: インペリアルレコード
- 発売日: 2007/05/23
- メディア: CD
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
近年はUSオルタナ・カントリーのウィルコと組んだウディ・ガスリー集を出しています。